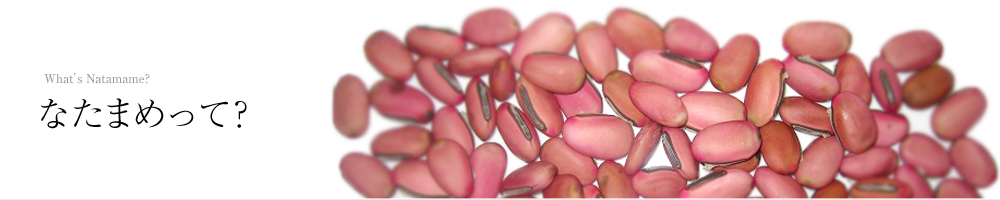

根粒菌は、マメ科植物の根に根粒(3〜5mmの丸いこぶのようなもの)をつくり、大気中の窒素を還元してアンモニア態窒素に変換し、宿主へと供給します。この「共生的窒素固定」を行う土壌微生物のことを根粒菌と言います。宿主(マメ科植物)からは光合成による産物(糖やデンプン)が根粒菌に供給され、共生関係が成立しています。
簡単に言うと…根粒菌は、宿主であるマメ科植物から栄養をもらい、マメ科植物の生育に必要なもの(窒素)を供給することでお互い利益を得ている=共生しているのです。
マメの種類によって、菌の種類も異なります。なかでもなたまめについては、どんな根粒菌が住んでいるのか、ほぼ未知に近い状態なのです。私たちはこのまだ正体のわかっていない、なたまめの根粒菌に注目し、学術面、応用面から研究をはじめ、現在、3年になります。
通常、畑の土には窒素が不足しがち。たとえばほかの野菜や植物をよりよく育てるためには、窒素、つまり化学肥料を人工的に施すという作業が必要になります。しかし、マメ科の植物は根粒菌のおかげでその必要はありません。このため、陽当たりの悪い湿地帯などいわゆる「耕作放棄地」でも、マメ科の植物なら育つという訳です。
ちなみに稲など、ほかの植物には根粒菌は付きません。
現在までの研究で、門出豆の根粒菌には大きく2種類あることがわかりました。ひとつはダイズ根粒菌に近いもの、もう一つはインゲン豆に近い種類のものです。ともに似ているけど違う「新種」の根粒菌であると考えています。
今後の研究では、優良な根粒菌、つまりより窒素活性が強いものを探し出すことが課題になっています。やがては、なたまめ以外の植物の種にも、化学肥料を使わずにこの根粒菌を振りかけて育てることで生育がうまくいき収穫量が増えるなどの成果が出て、生産者の役に立つことを夢見ています。

 |
〈齋藤先生のプロフィール〉 | |
|---|---|---|
| 1994年 | 東北大学農学部農芸化学科卒業 | |
| 1999年 | 筑波大学大学院博士課程修了(博士(農学)) | |
| 1999年 | 博士研究員(農業環境技術研究所、東北大学遺伝生態研究センター、オスナブリュック大学、農業生物資源研究所) | |
| 2004年 | 千葉大学 助手 園芸学部生物生産科学科 | |
| 2007年 | 千葉大学 助教 大学院融合科学研究科ナノサイエンス専攻 | |
| 2010年 | 現職 | |